「最近、母の様子が少しおかしい気がする」「同じことを何度も言うようになった」
高齢の親と接している中で、こうした変化に気づいたとき、多くのご家族が感じるのが“認知症かもしれない”という不安です。
実際、認知症は誰にでも起こり得る身近な病気であり、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。
大切なのは、早期に兆候に気づき、必要なサポートや「施設入居」という選択肢を検討していくことです。
本記事では、**認知症の初期症状(兆候)**と、介護施設に入るタイミングについて解説しながら、家族としてできる準備をご紹介します。
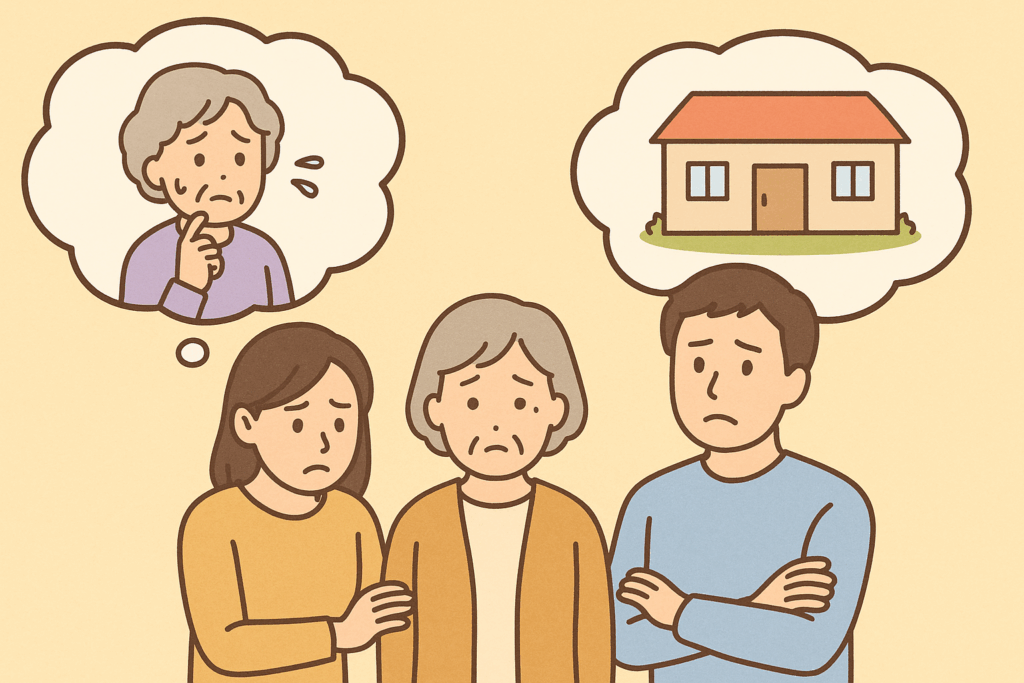
認知症の兆候とは?早期発見のために知っておくべき5つのサイン
認知症の初期段階では、以下のような変化が見られることがあります。
- 物忘れが増える
例:朝食を食べたことを覚えていない、約束を忘れるなど - 時間や場所の感覚があいまいになる
例:今が昼なのか夜なのか分からない、よく行く場所で迷う - 感情の起伏が激しくなる
例:些細なことで怒ったり、不安が強くなるなど - 身だしなみや家の中の片付けができなくなる
例:服が同じまま、ゴミが溜まっていても気にしない - お金の管理ができなくなる
例:同じものを何度も買う、詐欺に遭いやすくなる
これらのサインは、「加齢によるもの」と思われがちですが、日常生活に支障をきたす場合は注意が必要です。
家族が「いつもと違う」と感じたら、医師の受診や地域包括支援センターへの相談を検討しましょう。
施設入居を考えるべき5つのタイミング
認知症は徐々に進行していくため、自宅での介護が限界になることもあります。以下のような状況になったら、**介護施設の入居を検討する「タイミング」**です。
1. 本人が入居を望んだとき
自分の変化に気づいたご本人から「家族に迷惑をかけたくない」と希望されるケースがあります。
このタイミングで準備を始めれば、心身ともに余裕をもった施設選びが可能です。
2. 自宅での生活が困難になったとき
徘徊や火の不始末、排泄トラブルなど、安全確保が難しい状態になったときは、見守りが常時必要となります。
3. 介護者の体力・精神的限界
家族介護には、身体的・精神的な限界が伴います。腰痛や不眠、うつ傾向が出てきたら、家族の健康も守るために施設を検討すべき時期です。
4. 症状が進行し、在宅介護では対応が困難
怒りっぽさや幻覚、介護拒否など**認知症特有の行動・心理症状(BPSD)**が出てきた場合、専門的なケアが必要です。
5. 家族のライフスタイルが変わるとき
仕事復帰、引越し、介護者の病気など、家庭の事情によって介護が難しくなる場面もあります。
このような状況では、早めに情報を集め、複数の施設を見学することをおすすめします。
親の認知症が心配…兆候と施設に入れるタイミングを解説。グループホームや特養、有料老人ホームの選び方も紹介。高齢者支援NPOがサポートします。> 外部参考:介護施設に入れるタイミングとは?
施設の種類と選び方のポイント
認知症の方が入居できる施設には、いくつか種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| グループホーム | 認知症対応型、小規模、家庭的な環境 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上が対象、待機者が多い |
| 有料老人ホーム | 費用は幅広い、自立~重度介護まで対応 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 比較的軽度な方、自立支援中心 |
施設を選ぶ際は、本人の性格や症状、費用負担、将来的な介護体制も考慮しましょう。
> 内部リンク:
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の選び方と費用相場
認知症でも「納得できる施設選び」をするために
「親を施設に入れるなんてかわいそう」
「自分たちでできる限り頑張りたい」
そう思うご家族の気持ちは、当然のことです。
しかし、施設入居は「見放す」ことではなく、「安心の選択肢の一つ」です。
家族の負担を軽減し、本人の安全と尊厳を守るためにも、前向きに検討してみてください。
当NPO法人では、認知症対応施設の紹介・見学同行・入居後のフォローまでを一貫してサポートしています。
> 内部リンク:
入居前に確認したい!高齢者施設の契約書チェックポイント
ご相談はお気軽にどうぞ
「まだ早いかも…」と思っていても、早めに情報収集することが後悔しない第一歩です。
ご本人とご家族が安心して過ごせるための施設選びを、私たちと一緒に始めてみませんか?
▶ お問い合わせフォーム(24時間受付)
📞 03-6419-7597(平日9:00~17:00)
NPO法人 生活あんしんサポート
理事長 生田 忠士
東京都渋谷区東3‑23‑5 石川ビル2F
🌐 https://npo-seikatsu-anshin.com


コメントを残す