「自分は何歳まで働けるだろうか?」
そう考えたことはありますか?
日本人の平均寿命は延び続け、男性は82歳、女性は88歳を超えました。しかし一方で、健康寿命は平均で10年前後短いという現実があります。つまり、「働ける期間」と「生きている期間」には差があり、その間をどう暮らすかを定年前から考えておかなければなりません。
特におひとりさまの場合、年金・住まい・保険の選択を誤れば、孤独な老後に直結しかねません。今回は「何歳まで働くか」を起点に、老後を安心して暮らすための準備について解説します。
👉 関連記事はこちら:NPO生活あんしんサポートのブログ
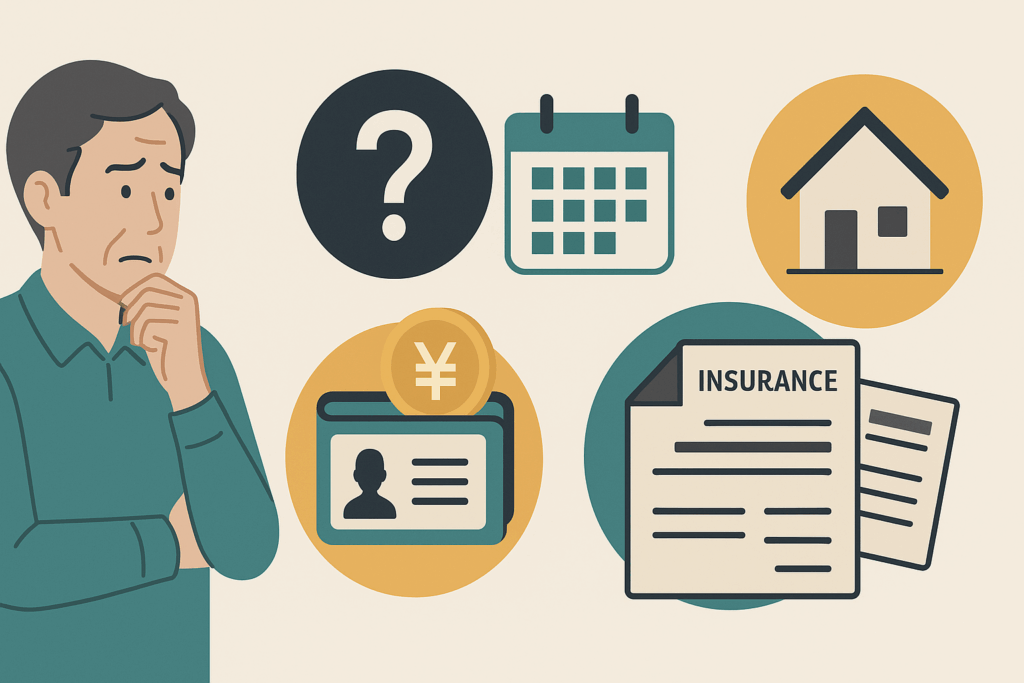
1. 何歳まで働くべきか ― 定年延長と再雇用の現実
多くの企業は60歳定年ですが、近年は65歳までの継続雇用が義務化されました。さらに70歳まで働く制度を導入する企業も増えています。しかし問題は、「体力とスキルが伴うかどうか」です。
- 60歳でリタイアした場合:年金受給までの空白期間をどう埋めるか。
- 65歳まで働いた場合:厚生年金が増える一方で、心身に無理が出やすい。
- 70歳まで働く場合:体力・職場環境・スキル更新の難しさが大きな壁。
「働けるうちは働く」という選択肢は悪くありませんが、それが現実に可能かどうかは人それぞれです。むしろ大切なのは、「働けなくなった場合」を想定し、年金や資産計画を早めに立てることです。
👉 参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法」
2. 年金 ― 受給額を正確に把握していますか?
「年金だけでは暮らせない」――よく聞く言葉ですが、まずは自分がいくらもらえるのかを知ることが第一歩です。
- ねんきん定期便で確認:毎年送付される「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で試算が可能。
- 繰り下げ受給の検討:65歳からの受給が基本ですが、70歳まで繰り下げれば42%増額されます。
- 受給開始年齢の調整:生活費や就労状況に合わせ、いつ受け取るか戦略的に考えることが重要です。
「年金が足りない分をどう補うか」を考えることで、老後の安心度は大きく変わります。
3. 住まい ― 最後まで暮らせる家を選ぶ
老後の不安で大きいのは「住まい」です。
実際、独居老人の孤独死の多くは「老朽化した持ち家や古い賃貸」で発生しています。
選択肢は大きく3つ。
- 今の家に住み続ける
バリアフリーリフォームや耐震補強を行い、安心して暮らせるように整備する。 - 住み替え
利便性の高いマンションやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に移る。 - 施設入居を視野に入れる
将来的に介護が必要になることを前提に、費用や条件を調べておく。
👉 参考:国土交通省「高齢者の住まい」
4. 保険 ― 本当に必要な保障を見直す
現役時代は「死亡保障」や「子育て資金」のための保険が中心ですが、定年前後からは必要な保障が大きく変わります。
- 医療保険:高齢になるほど入院リスクが高まり、医療費の自己負担も増加します。
- 介護保険:介護が必要になったとき、どの程度公的保険でカバーされるかを確認し、不足分を補う民間保険を検討。
- 生命保険の整理:独身で子がいない場合、多額の死亡保障は不要。見直すことで支出を減らせます。
無駄な保険料を払い続けるのではなく、老後に必要な保障だけを残すことが賢明です。
5. 孤独を避けるために ― 「備え」と「つながり」
年金・家・保険を整えても、孤独死のリスクは消えません。
実際、東京都監察医務院の調査では、年間3,000人以上が「孤独死」として扱われています。
解決策は、定年前から地域や人とのつながりを持つことです。
- 見守りサービスを導入する
- 地域活動や趣味のサークルに参加する
- 信頼できるNPOや専門家に相談しておく
👉 関連記事:見守り・身元保証に関する記事
まとめ ― 定年前に「行動」するかが未来を変える
「何歳まで働けるか」ではなく、「働けなくなったときにどう生きるか」。
これが本当に重要な視点です。
年金の受給額を知ること、住まいを整えること、保険を見直すこと。
そして孤独に備えて人とのつながりを作ること。
これらはすべて、定年前から始めなければ間に合いません。
私たち NPO法人 生活あんしんサポート では、老後資金の相談から住まい探し、身元保証や見守りサービスまで幅広くサポートしています。
将来に少しでも不安を感じる方は、今すぐご相談ください。小さな一歩が、安心の老後をつくります。
NPO法人 生活あんしんサポート
理事長 生田 忠士
東京都渋谷区東3-23-5 石川ビル2F
🌐 https://npo-seikatsu-anshin.com


コメントを残す