高齢化が急速に進む日本社会では、認知症や判断能力の低下に備えるため「成年後見制度」が広く利用されています。
本来は大切な財産や生活を守るための制度ですが、最近では制度の運用を巡る「トラブル」や「家族の分断」といった深刻な事例も報道されています。
今回は、Yahoo!ニュース(集英社オンライン)で報じられた記事
👉 〈成年後見制度の闇〉居場所も伝えず高齢母を老人ホームに「軟禁」…全国で相次ぐ高齢者の連れ去り被害や金銭トラブルの実態とは
を取り上げ、NPOとして感じる課題と、皆さまに知っていただきたいポイントをまとめます。
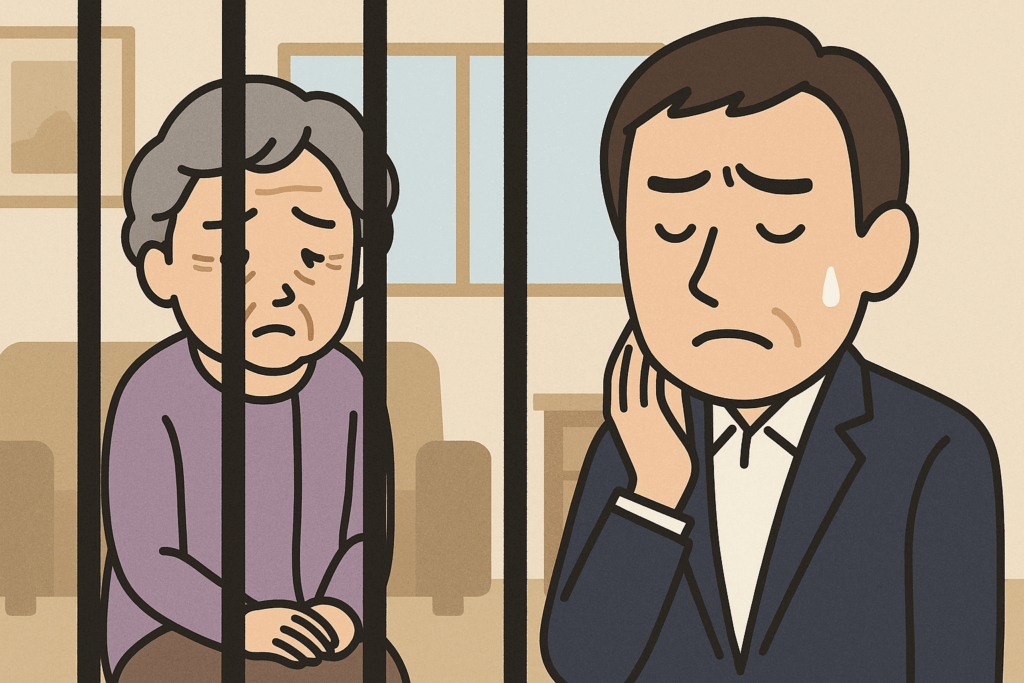
報道された事例の衝撃
記事では、80代の認知症のお母さまが、家族の同意や居場所の告知もないまま、後見人によって老人ホームに移されてしまったケースが紹介されています。
家族は必死に探しましたが、後見人である弁護士からは「居場所は伝えられない」と突き放され、結局数か月後に遠方の施設で生活していることがわかったとのことです。
成年後見制度は「本人の生活・財産を守るための制度」であるはずですが、現実には「家族との断絶」「本人の意思の無視」という形で悪用されてしまう危険があるのです。
制度の仕組みと問題点
成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります。
- 任意後見制度
元気なうちに信頼できる人を後見人に指定する制度。本人が意思を示せる段階で契約するため、比較的トラブルが少ない。 - 法定後見制度
判断能力が不十分になってから家庭裁判所が後見人を選任する制度。現在の利用の98%以上はこちらで、弁護士や司法書士といった専門職が選ばれることが多い。
問題はこの「法定後見制度」に集中しています。
報酬体系が「預貯金が多いほど後見人報酬が増える」仕組みになっており、財産の現金化や不要な施設入居を強要するなど、被後見人本人にとって不利益な判断が行われるケースが散見されます。
家族ができる備え
私たちNPOにご相談いただくご家族からも、
- 「後見人に選ばれた弁護士と連絡が取りにくい」
- 「母の施設入居を勝手に決められた」
- 「生活費が渡されず、本人が困っている」
といった声が寄せられています。
制度を利用する際に大切なのは、本人の意思を尊重すること、そして信頼できる人を事前に選ぶことです。
任意後見契約を早めに結んでおくことで、「知らない専門職に突然任される」というリスクを減らすことができます。
👉 関連記事:身元保証契約のリスクと注意点を解説(当法人ブログより)
NPOとしてできること
私たち NPO法人 生活あんしんサポート では、成年後見制度や任意後見制度についてのご相談を受け付けています。
- 制度の違いをわかりやすく説明
- ご家族の意向を尊重しながら契約書作成や手続きの支援
- 信頼できる後見人・保証人探しのお手伝い
- 高齢者施設の紹介や入居支援
単に制度の知識だけでなく、生活全般の安心を支える伴走者としてご利用いただけます。
まとめ
成年後見制度は、適切に使えば高齢者を守る大切な仕組みです。
しかし実際には「連れ去り」「財産管理の不透明さ」「家族との断絶」といった問題も起きているのが現実です。
- 早めに任意後見を検討すること
- 制度を正しく理解し、信頼できる相談先を持つこと
- 家族で意思を共有しておくこと
この3つが、安心して老後を迎えるために欠かせないポイントです。
制度や施設選びで迷った際には、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。
👉 NPO法人生活あんしんサポート公式ブログ
無料相談受付中 お気軽にご連絡ください
NPO法人 生活あんしんサポート
理事長 生田 忠士
東京都渋谷区東3-23-5 石川ビル2F
🌐 https://npo-seikatsu-anshin.com


コメントを残す